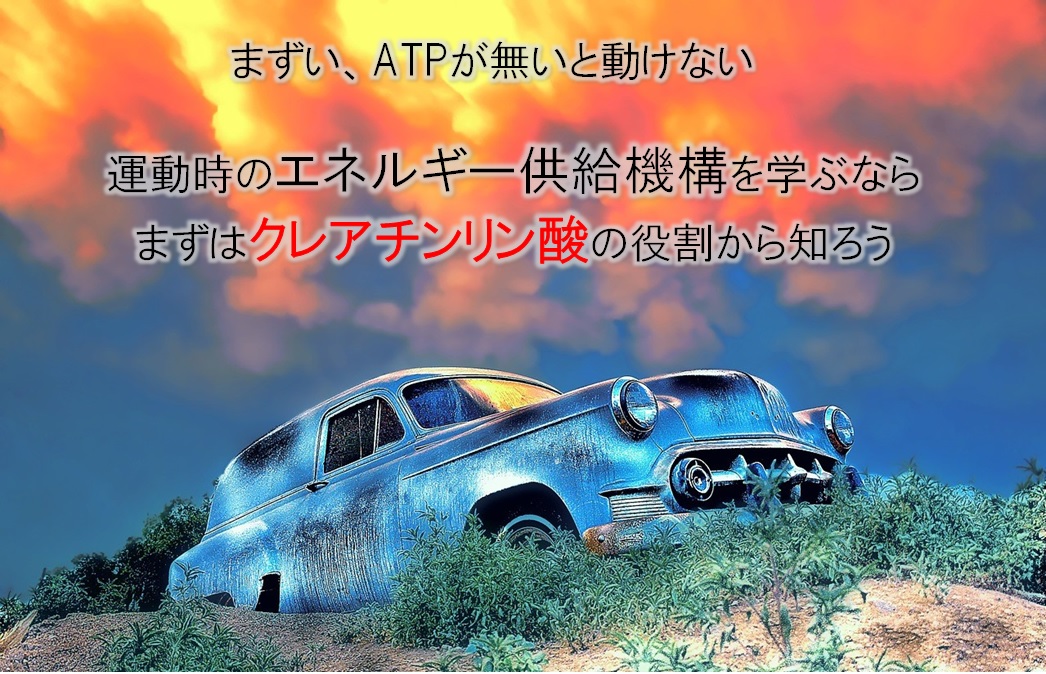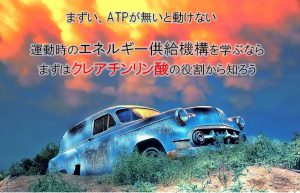こんにちは。
川﨑文也です。
「トレーナーの基礎力が向上する」1日3分の流し読み問題集no.15
では、今日も問題です。
問題
ATPを無酸素で再合成するシステムを「ホスファゲン機構」と呼ぶ場合があります。
では、ホスファゲン機構に含まれない物質はどれ?
A クレアチンリン酸
B 乳酸
C アデノシン三リン酸
D アルギニンリン酸
――――――――――――――――
正解: B 乳酸
『ホスファゲン』とは、エネルギーを蓄えているリン酸の事をいい、○○リン酸と呼ばれている物質の総称になります。
なので、ホスファゲンとはグループ名や、苗字みたいなイメージです。
磯野さん家の、ワカメちゃん。
野比さん家の、のび太くん。
ホスファゲンの、クレアチンリン酸。
・・・みたいなイメージです。
さてさて、無酸素でATP(アデノシン三リン酸)を再合成するシステムでは、クレアチンリン酸の働きが重要になってきます。
では、クレアチンリン酸はどんな役目があるのでしょうか?
ATPの分解から再合成まで順を追って確認していきましょう。
ヒトが体を動かす時には、筋肉を収縮させるためにエネルギーが必要になります。
そのエネルギーはATPが分解される時に生み出されます。
つまり、筋肉を収縮させるためには、ATPを分解し続けないといけない。
ということになります。
分解されたATP(アデノシン三リン酸)は、ADP(アデノシン二リン酸)とPi(リン酸)に分かれます。
[aside type=”pink”]ATP → ADP + Pi + エネルギー[/aside]
ATPやらADPやら、似たような言葉がならんで覚えにくいですよね。
なので私はこんな感じで覚えていました。
ATP(エー・ティー・ピー)は
【A】アデノシンと、
【T】トリプル(三つ)の
【P】リン酸(Pi)がくっついいる。
*本当のATPの頭文字は adenosine triphosphate です。
ADP(エー・ディー・ピー)は
【A】アデノシンと、
【D】ダブル(二つ)の
【P】リン酸(Pi)がくっついいる。
*本当のADPの頭文字はadenosine diphosphateです。
話が逸れてしまったので、本題に戻ります。
筋収縮を継続するには、ATPを分解して、エネルギーを作り続けないといけないわけですが、分解ばっかりだとATPが無くなってしまうので、分解作業と並行してATPを作り出す作業が必要になります。
ATPを「使う量」と「作る量」のバランスが取れていると筋肉は動き続けることができますが、使う量の方が多くなるとATPが無くなってしまい、筋肉は動けなくなるので大問題になります。
ここで、クレアチンリン酸が活躍してくれます。
ATPから分解されて、リン酸が少なくなったADPに、クレアチンリン酸が持っているリン酸を分けてあげます。
そしてADPは、クレアチンリン酸から分けてもらったリン酸を自分に取り込むことで、ATPに戻る(再合成する)というわけです。
[aside type=”pink”]ADP + クレアチンリン酸 → ATP + クレアチン[/aside]
と、いうわけでクレアチンリン酸はATPを再合成するために活躍してくれるということです。
この、クレアチンリン酸を使ってATPを再合成するシステムが
「フォスファゲン機構」や、
「ATP-CP系」
「非乳酸性機構」
なんて表現で呼ばれています。
しかし、クレアチンリン酸だけではATPの「使う量」と「作る量」のバランスを保ち続けることはできません。
ATPもクレアチンリン酸も体内に少量しか蓄えられていないので、すぐに「使う量」の方が多くなります。
なので、短時間しか「使う量」と「作る量」のバランスを保てないのです。
高いパワー発揮のトレーニングを積むと、筋中のホスファゲンの量を増やすことは可能ですが、それでも限度があります。
では、「使う量」と「作る量」のバランスを保ち続けるためにどうすればいいのか?
クレアチンリン酸以外の手助けが必要になってくるわけですが・・・
長くなるので、続きは別の機会にしたいと思います。
それでは、今日はここまで。
今日のまとめ
- フォスファゲン機構とは、リン酸を使ったエネルギー供給システムのことであり、他には「ATP-CP系」や「非乳酸性機構」なんで呼ばれ方もする。
- クレアチンリン酸のリン酸を使って、ADPからATPに再合成される。
- クレアチンリン酸でのATP再合成は短時間しか機能しない。
=================
「トレーナーの基礎力が向上する」1日3分の流し読み問題集は、私が学生時代に後輩たちに向けて配信していたメールマガジンです。内容はNSCAの教本をもとに作成しています。分かりにくい生理学や解剖を少しでもイメージしやすいようにまとめていきます。何かお役に立てれば幸いです。
=================